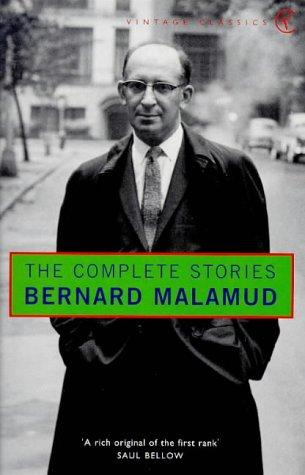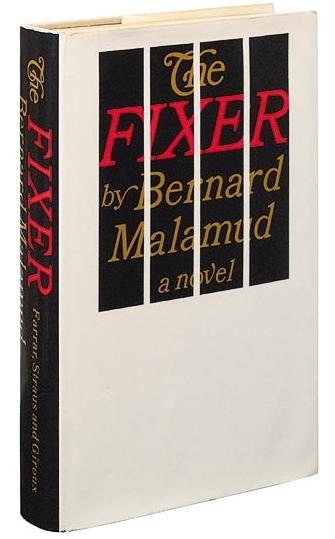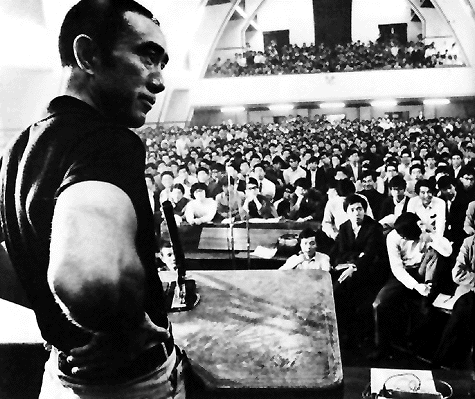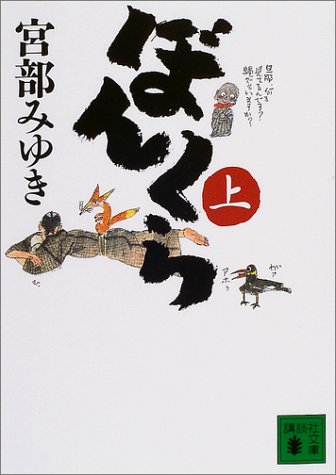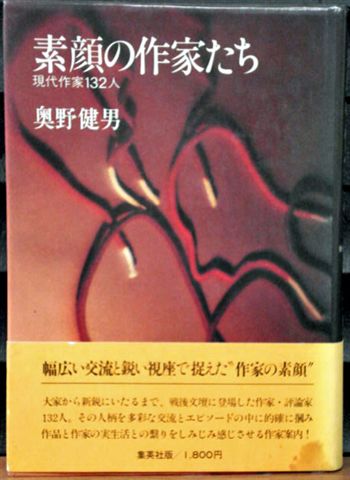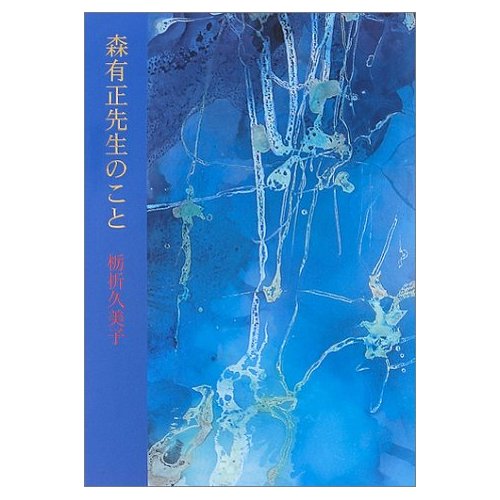�}�[�t�B�[�̖@���i�����ҁF�}�[�t�B�[���m�j �܂����Ȃ�\���̂�����͕̂K���܂����Ȃ�B
�m���߁n�@�A�����J�ōł��|�s�����[�Ȑl���@���B���̔����ҁE�}�[�t�B�[���m�ɂ��Ă͏������X�ŁA�q��
�����̊J���Z�t�A�̑�ȋ��t�A���_������ւ̊҂Ȃǂ̏،����Ȃ���Ă��邪�A�^���͕s���B�ǂ�����z��̐l���ł͂Ȃ����A�Ƃ���
�������邪�A����A�䂪���{�Ŕ��m�����ʒ��O�ɑΒk�����A�Ƃ����{�i�w�}�[�t�B�[���m�̍Ō�̌��t�x�j���o�ł���A�c�_�͎~�܂�Ƃ�
���m��ʁB�Ȃ��A���̖{�ł̃}�[�t�B�[���m�́A�A�C�������h���܂�ŕ٘_�p���w��1981�N���S��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��褎ʐ^�܂ł���
�Ă����ɂ��ނ��炵���̂ł���
�@�ȏ㤂�������e�����ɂ����f����ȁf�Ƃ����o�傪������꤃A�����J���������̔ɉh�ͤ���͂������������������F���̏�ɐ��藧�� �Ă���̂���Ƃ������Ƃ��f�킹�Ă���顂����ɤ�A�����J����v���O�}�e�B�Y���̐��������餂ƌ����Ă��悢���낤� |
||||
 |
 |
�}�j�s�����[�V�����̖@���i�����ҁF�r��Ď��j �K���ȁu����v�ɂ�艽�����Ǘ����\�ł���B
�m���߁n�@Manipulation���������죂ł��顐g�̂̑���Ńt�B�b�g�l�X��s��̑���Ń}�[�P�e�B���O����K��
����ɂ�萢�E�͑��c�\�Ȍn�ɂȂ餂Ƃ����l�����Ť������܂��@���ɂ��A�����J�I�@���ł���
|
||||||
 |
 |
�}���}�b�h�́u�����v�̖@���i�����ҁF�a�D�}���}�b�h�j �ȑO�̏�Ԃ��ň��Ǝv�������A���͂����ƈ����B
�m���߁n�@���_���n����}���}�b�h�������u�t�B�N�T�[�v�̎�l���Ɍ�点�����z�ł���B
�鐭�����̃��V�A�ŁA���}�ȃ��_���l�̏C�������[�R�t�����N�E���̋^���œ����B�̓Ɩ[�ɓ����ꂽ�ނ̏�ɁA���̎�����L�̐l��I�E�����I���Q����������B�����ď��X�ɕǓI�ȏɒǂ����܂ꂽ���[�R�t�́g�O�̏��ς���������A���͂���������ƂЂǂ��h�ƒQ������̂ł���B���́A��]�̉��ɂ���Ȃ���A�Ȃ������ȃ��[���A������������̂��}���}�b�h���B�����ɂ́u���_���l�Ƃ������̂͂����߂���̂��v�i�u���@�̒M�v�̐_�w���̏q���j�Ƃ�����҂̉��₩�Ȓ��ς�����B�܂����̍l�����́A�O�o�u�S������̖@���v�����u�Δ�̖@���v�i�g�������ƈ����ꍇ�Ɣ�ׂ�h�j�̃��@���G�[�V�����Ƃ��������悤�B�������́g�h�������ɋN����Ƃ��낪�A���Ɓu��r�v���ɂ����킯�ł����c�B [��]�@�O�o�C���t���y�g���t���t���[�h�}�������������_���n�B������}���}�b�h�Ɏ����g���邢�ߊώ�`�h�̎�����ƌ����Ă悢�B�i�������ւ̔��Q�̗��j���Y�����q�̃��[���A�ł���B |
||||||
 |
 |
 |
 |
|||
�O���R�I�v�́u�~�]�ƈӎu�v�̖@���i�����ҁF�O���R�I�v�j �u�~�]�v�Ƃ́u�f�łƂ��Ė]�܂ʂ��Ƃ���萋�������v�Ǝv�����Ƃł���A�u�ӎu�v�Ƃ́u���̗~�]�����Ƃ��Ă����������邱�Ɓv�ł����B
�@�c�����̎O���́A�c��E��e�̓M���A���ؑ��Ƃ����ƕ����́u��v�̉��A�g���̒��̉��q�h�Ƃ��čK���������B�����Ă��̉��q�̐��I �n�D�́A���w���̎�҂̓��̂ɗ~���A�Ƃ����ُ�Ȃ��̂ł������B �A���̂܂܂ł͋���ȕ��w�I�_���ɂƂǂ܂邪�A�O���͂��̗ދH�ȓ��]�Ǝ��ȍ����̈ӎu�ɂ��A�����I�Ȑ����i���呲�̑呠�L���� �A�I�j�������߁A����̐��I�n�D�𐢊Ԃ�������Ȃ��悤�ɂƊ�ށB����Ɂe�X�p���^���P���f�ɂ����̉����𐋂��A���ē��� ���w�F�x�̓�I���w�ߌ�̉g�q�x�̗���̂悤�ȁe��m�f�ɕϖe����B �B���������́e�ώ@����O���f�i�Ⴆ�w�t�̐�x�̖{���ɖM�j�Ɓe�s������O���f�i�������A���}�����j�́A�����܂� �u����̒��̎����̕���v�ɉ߂����A�����ɂ́A�e���҂Ƃ��Ă̏����f�͂��ɑ��݂����Ȃ��B���̂�����̎������Ԃ킩���Ă���͍̂�� ���g�ŁA�w�L�`�̊C�x�l����̖����Ɏ���A���}�����̈��l���������q���q�Ɂu�i����Ȑl�́j���Ƃ��Ƃ��炵���Ȃ������̂ƈ�Ђ܂� ���v�ƁA�O�����g�A�����č�i���̂��́A�܂ł��S�ے肳����̂ł���B �@ �@���Ȃ킿�O���́A�{���̎����ɖO�����炸�A��L�@���̔@���}�]�q�X�e�C�b�N�ȁu�~�]�ƈӎu�v�ɂ��]�܂���������グ�����A ����́u����̒��̕��������v�ɉ߂��Ȃ������B�����āA������߉ނ̎�̒��̌��A�ƌ�����ނ́A�u��i�O�̌���������������� �f�v����v���Ƃ�]�݁A���ɂ�������s�Ɉڂ����̂ł���B���̎��A�\���搂����u�[�ȗ[��/���ӂɗ����҂���/�֎��v�́A�҂��]�� �ނ̉��ɐÂ��ɖK�ꂽ�̂ł��낤���B [��]�@�O���́A�e������D���l�ԁf�Łi�܂��A����ɒl���邾���̖��͓I�ȁu���ȁv�ł͂����� ���j�A���ɂ͂��������e�j�ōD���̎����f�ɏ}�������ƂɂȂ�B���{��ƁE���R�J�̖��ƌ����A�K���ȉƒ���c��ł���悤�Ɍ����Ȃ� ��A���͔ނ̐S�Ɂe���҂Ƃ��Ă̏����f�͑��݂����Ȃ��B�����Ĕނ��A�u�����Ƃ͑���ƂЂƂɂȂ肽���Ƃ����Փ�������A���� ������j�́A���ɂȂ肽���̂ł���v�ƒf����Ƃ��A�����͌����Ă��̂悤�ȁu�����v�����Ȃ��A�ƐS�����ɐ����Ă����Ǝv����B������ ���̗����ɂ��Ẳs�����͂́A�O�f�E�c�������f�C���u�w�r���x�̖@���v��A��f�u���J ���̗~�]�̖@���v�Ǝ�����u�Ăċ��������Ă���̂ł���B�@ |
||||
 |
 |
 |
 |
|||||
�{���݂䂫�̢�~��̖@�� (�����ҁF�{���݂䂫) �ʂ��O���狯���ĕ�炷�̂́A�ʂꂪ�|���̂ł͂Ȃ��A�����̎�ɂ������̂����������Ȃ��Ƃ����~�ɁA�U���ĂĂ��邾�����
�m���߁n�@����~�X�e���E�̏�����{���݂䂫���a�����A�Ӑg�̎���~�X�e���w�ڂ�x�A�w����炵�x�Q����̈�߂���B
[��]�@ �{�V���[�Y�́A�����o��l�������͓I�B���l�Y��|�V���R���r�̌ċz���▭�����A���̗͋��������́u���ł��v�Ɖ������E���ܘY�̑��`�������ł���B���Ɂu���ł��v�́A���ق̋L���͂����u�l�ԃe�[�v���R�[�_�[�v�Ƃ����ݒ�ŁA���N�z�̋|�V���̐e�F�ł�����i�Q�l�Ƃ��A���̈ٔ\�Ԃ�ɂ�����炸�g���N�炵�����X�����h��ۂ��Ă���Ƃ��낪���܂����j�B ���̘A�쎞�㏬���́A�~�X�e���̍��@���V�b�J���Ɖ������Ă���_�ł��o�F�B
�V���[�Y�`���̒Z�ҁu�E�����v�ł́A�^�C�g���u�E�����v�́g�d�w�I�ȈӖ��h�̉�ǂ��N�₩�����A�{���i�Ƃ��сj�����钆�сu����炵�v�ł̓��@���E�_�C���̏����̖�����v�킹�������ɚX�炳���B
�����ĉ������A�I���߂��A�|�V��������U��i���Č�鎟�̌��t�̏Ռ��\�\�A
�u�ق�̙��߁i���ȁj�ł������܂����A����ȋꂵ����炵�����Ă���l�����̑O�ł́A�N����������E�������������R�ł��낤���A����Ȃ́A�����������ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��܂����v |
||||||
 |
 |
 |
 |
|||||||
�����Ґ��̢���l��̖@�� (�����ҁF�����Ґ�) ���l�͑�������ł͂Ȃ�Ȃ�
�m���߁n�@�����Ґ��ƌ����A��W�w�R��ȏW�x���̈�߁u�ӂ邳�Ƃ͉����ɂ���Ďv�ӂ���/�����Ĕ߂��������������v�i�u���i�ُ�v�j���L���ȝR��l�B
���̔ނ��ӔN�ɒ������w�䂪�����鎍�l�B�̓`�L�x�́A�e���̂��������l�B�ւ̈���ӂ�錆��]�`�ł������B�����Đ�Ɏ���ł��������ԒB�Ɍ����A�Ґ�������������t����́g�@���h�ł���B�k�����H�T�V�A�����Y�T�U�A�x�C�Y�S�X�A���������Q�S�A�Ñ��M�v�R�T�A�R���钹�S�O�\�\�{���Ŏ��グ��ꂽ���l�̓��U�����җ��҂��������B���Ɏt�̔��H�A�e�F�̍Y�̑����́A�Ґ��Ɂg���l�͑����ɂ���h�̋C�����������炵���Ǝv����B����͎��̊ԍۂ܂Ŏ��M�ӗ~���������A�u�ӔN�̎d���i�����j�ɂ��A�Ґ��͓�����̂��ׂĂ̕��w�҂��A�J�菁��Y�ƕ��ԁA���邢�͂���ȏ��
�吳�Ȍ�̍ő�̕��w�҂ɂȂ����v�i���쌒�j�u�f��̍�Ƃ����v�j�Ə̗g���ꂽ���A�������㒷�������������Ƃ݂�A���̌��t�̈Ӗ��͐[���B
[��]�@ ��ň��p�������쌒�j�u�f��̍�Ƃ����v�́A�]�_�ƁE���삪�t�������̂����Ƃ��������グ�A���́g�f��h���Љ�����́B�o�ꂷ�镶�w�҂P�R�Q�l�A�A�ڊ��ԂP�W�N�ɋy�ԘJ��ł���B�Ҏ҂͂��̖{�ŁA�k�����v�A�D�������A�a�c�F�b�Ƃ����������w�ł͂��܂�Ȃ݂��Ȃ���Ƃ����̐^�������߂ċ�����ꂽ�B ����̗����ȕ��������e��Ƃ̖{���𖾂炩�ɂ���g���]�_�W�h�ł���Ǝv��.�@ |
||||||||
 |
 |
���V���́u���v�̖@���i�����ҁF�q�D���V���j �@�q���Ƃ����ЂƂ�̐l�Ԃ́A�e�ɂƂ��āA���̓����̖{�����A�����̓��ɍ��E�����Ɠ��l�ɁA���̓��̂ɍ��E�����A���̓��̂̋Q���A���A���o�A���o���A�e�̂���ƌ��т��A�Ƃ������I�ȑ��݂ł���B�A���͂�����l�Ԃ̂��߂̂��̂ł��邩�̂悤�ɁA�����������ɂ�������l�̐l�Ԃ̂��߂̂��̂ł��邩�̂悤�ɑ��݂�����B [����]�@���x���g�E���V���i�o���̃`�F�R��ǂ݁B�h�C�c��ł̓��W�[���j�́A�v���[�X�g�A�W���C�X�ɔ䌨����I�[�X�g���A�̏����ƁB���̖����̑���w�����̂Ȃ��j�x�́A�Q�O���I���w�ɛ��������勐��ł���B�Ȃ����V�����g�́A�v���[�X�g�A�W���C�X�ɂ��āu�n���������̂�`���Ă��邪�A���ۂ̎�@�́A���Ď����̂͂����肵���֊s��M���Ă������ƁA�S���������v�Ǝ茵�����B�܂��ɁA�u���M�ȏb�i�������A�����Ȉ�N�Ԃ̊����̌�͂T�N�Ԃ̓~�����K�v�j�v�i�e�D�u���C�j�ƕ]���ꂽ���V���̖ʖږ��@�ƌ����ׂ����B����ŁA�ꍑ���w�E�ł��������Ƀ��V����M���Ȃ���h�����āA�u�w�����̂Ȃ��j�x�́A�������I�A�V�X�̂��鍻���̂悤�Ȃ��́v�Ƃ�������B�܂�A�I�A�V�X�͑f���炵�����A�I�A�V�X�Ԃ̈ړ��́u�炢���Ƃ������v�i�l�D���C�q�����j�b�L�j�Ƃ����킯�ł���}�X�B
�@���u�O�l�̏��v�̈�l���u�O���[�W���v�̎�l���z�����A�����n�ŕa�C�×{���̑��q�Ɏv����y�������A���R�ɗN���o�����S�ł���B�����ȊO�͑S�āg���l�h�̂��̐��E�ŁA�q�������͗B��́u�����̖{���v�����L���鑶�݂Ȃ̂��A�Ƃ����[���\���́u���l�Ƃ͈Ⴄ�ʎ�̑����v�ɂ���āA��l���́u��̋^����Ƃꂽ�V��̔�ւƂ��āA�����o���v����̂ł���B ���̃��V���ꗬ�̌��S�ȕ��͂�Ҏҗ��ɓǂ݉����A����Ɠ����c�m�`�����q���Ƃ������݂��A�l�Ɉ��̉\����M��������A�Ƃ������ƁB�m���ɁA���l���炯�̂��̐��E�ōł�����ɋ߂��̂́A�����̎q���ɑ��Ȃ�Ȃ��B�q�������́A����Ƃ��̓��̂̋Q�����J�A���o���o�����ڂɂȂ��肠���Ă���u��ՓI���݁v�i��������V���́u���I�v�ƕ\������j�Ȃ̂ł���B �A�́A�u���̊����v�ňÎ������g���̃p���h�b�N�X�h�ɂ��Ă̍l�@�ł���B�l�́A����̐l���������Ă��Ă��A�����̏�ʂł͍L�͂ȑ��҂Ǝ��R�Ɂi�b�̂悤�ɁI�j���ѕt�����Ƃ��ł���B�����������ɂ��u�b�Ƃ��Ă̌ǓƁv������B����ŁA�l�͓���悤���Ȃ��u�����v���b�i���т��j�̒��ŁA�u���Ԃ̌ǓƁv�������킴��Ȃ��B���������u�ǓƁv�ɑł������߂Ƀ��V�������������́A�g�قƂ�Ǐ펯�̗�����₷���g�i�쑺��Y�j���@�ł������B���Ȃ킿�A�P��I�Ȉ��̃p�[�g�i�[�V�b�v��ۂ��Ȃ���A���R�Ȑ����̉\���ɐg�𓊂��鎞�A�l���u�ǓƁv����������A�u���������v����A�Ɛ����̂ł���B �܂��ڑ��Ɍ���A���C�̍m��Ƃ����ꂩ�˂Ȃ����������A�O�f�u�O���[�W���v�ł��A��l���z�����R�̏��O���[�W���Ə���d�˂邱�Ƃɂ���čȂƂ̈����Ċm�F����A�Ƃ�����ʂ�����A��҂��u���̐_��v�ɂ��čl�@�������̐M�O�Ȃ̂ł���܂��傤���B
[��]�@���V���̒���ɂ́A ��L�́g���ɂ��Ă̏Ȏ@�h�ȊO�ɂ��A���X�́u����ۂނقǂɂ߂��܂�����g�v�i����K�g�j���p�o���邪�A�ȉ��ɂ��̈ꕔ���f���ă��V���̓V�˂Ԃ�𖡂���Ă݂����B �E�u�l���ɂ́A��ɕ��������߂āA�O�i�����߂���Ă���̂ł͂Ȃ����A����Ƃ�������]���悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����悤�Ȉꎞ��������B���̂悤�Ȏ����ɂЂƂ͕s�K�ɂ������肪���Ȃ��̂炵���B �v�i�u�O���[�W���v�ȉ��A�S�Đ쑺��Y��j �\�悭�킩��Ȃ��̂����A���������������ėL��悤�ȋC�����Ă��邩��s�v�c�B���V���̕��͂̏����ł���B �E�u�^������������ł��������ɁA��邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�₪�Ă��Ƃ������̂�҂������āA�������܂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B�v�i�u�|���g�K���̏��v�j �\�ЂƂ͉^���ɑ������ł���A�Ƃ����v�����A���V���̎v�l�̍���ɂ���悤�ȋC������B �E�u�Ƃ���r�_�̂قƂ�B��H�̒��������������B�Ǝv���Ƒ��z�́A�����M�����̂ǂ����Ɏp���������Ă����B�[�����B�S�����������̂��������Ȃ����������ė����B����ȏ������͂��ǂ����āH�����A ���̂悤�Ȉꕔ�n�I���A�܂�ŌI�̂������Ȃ̂悤�ɁA�l�̐S�ɂ܂Ƃ����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����A����͍��ׂȂ��Ƃ��낤���H���ꂪ�A�g���J�������B�����Ƃ������̂́A �����A�ЂƂ��������H�藎������̂ł���B�v�i�u�g���J�v�j �\�g���J�͌���A���R�̉��g�ł���A�Ƃ������Ƃ�\��������������߁B�|�p�Ƃ͂��ɁA����������u���Ƃ炦�邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ���v�킹�錩���ȕ`�ʂł���B�����ɂ́A���̊Ԃ̕��a�̂����Ɍ��o���ꂽ���R�̔�����������B �E�u�����Ƃ������̂́A���߂�����ꏊ������킫�܂����ɋN������̂ł����B�v�i����j �\���̊������[���B���̌�A�{���́u����Ȏ��ЂƂ��i�����j�N�����܂��Ă���Ȃ��i���̂悤�ɖ��͂ɂȂ��v�Ƒ������A���̔�g���܂��G��B �E�u�ޏ��i�g���J�j�͐��_�ɂ��]�����R�������B�݂����琸�_�Ɖ����邱�Ƃ͊��Ȃ����A���_�������A�����Ȃ炳��ĉƒ{�ɂȂ�����b�̂悤�ɁA�Ђ��Ɛ��_�ɂ�肻�����R�������B�v�i����j �\�����A�g���J�Ƀ}���^�v�l�̖ʉe���d�Ȃ�悤�ȕ`�ʂł���B �E�u�l����Ƃ́A�l�������Ȃ����Ƃ��B���肠�܂�˔\�𑽏��Ƃ��}�����邱�ƂȂ��ɂ́A�����Ȃ锭�����s�\�ł���B�v�i����j �\����́A�g�����̐^���̂��߂ɂ͐ٗ��疟�������Ȃ��h��Ƃ̌��Ƃ��Ă͈ӊO�B���V�����g�̎����̔O�ł��낤���B �����čŌ�Ɂi�]�҂ɂ͓�́j��߂��B �E�u�g���J�́A���R�Ƃ������̂��A���̐��̂悤�ɂ������ɂȂ��Ă��т��������Ă���A�����₩�ȏX�����̂���łł��Ă��邱�Ƃ����������낤�B�v �\���܂ł̕����Ō����g�������h�͂��̎��R���A�u�X�����́v�Ɗ�������͉̂��̂��H�@�Ҏ҂͂��̓ˑR�̕ϖe�Ɍ˘f�����A�����������ʓI�ȑ��������A�܂����V���炵���ƌ����Ό�����B���邢�́A���Ȃ�ʁg���R�̉��g�h�g���J�̂ɁA�������Ď��R�̏X���{�������������Ƃ������Ƃł��낤���H�@����ɂ��悱�̍�ƁA��ؓ�ł͂����Ȃ��B |
||||||||
 |
 |
���C�E�T�[�g���́u���́v�̖@���i�����ҁF���C�E�T�[�g���j ���̂͐��Ȃ���̂ł���B[����]�@���C�E�T�[�g���i1912-95�j�́A�x���M�[���܂�łS�̂Ƃ��A�����J�ɖS�����������ƥ���l��G�b�Z�C�X�g�B �w�Ƃ苏�̓��L�x���|��o�ł���Ĉȗ��A���̎��R�ւ̎]�́A�Ǎ��̎v����������ǎ҂������B���@���́A����ȃT�[�g�����U�U�̎��� �����̎�p������A�������ƉɌ����Ă��鎞�ɕ������[�����S�ł���B �@�u�g�͉̂F�����̂��̂ł���A�ǂ̂悤�ȑn�����A�s�v�c�Ȃ�����������⍩������ՂȂǂƂ��������Ȃ���̂Ƃ݂Ȃ���Ȃ���� �Ȃ�Ȃ��B���̂����Ȃ���̂ł��邱�Ƃ�Y��Ă͊댯���c�c�B�v �@���f�b�J�`�ɂȂ�������l�́A�ēx�A���̂̎��̑�ȗ͂Ɏv���������˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B [��]�@����قǂ� ���x�Ȏv���̐l���A���ɓ��̂̎��R�ȗ͂�O�Ɏv�l��������A�������Ȃ�g�̂��]������A�Ƃ����ԓx����ۓI�ł���B�O�f�u�w�[�m���̋t���x�̖@���v�ɒʂ���o��ƌ����Ă悢�B |
||||
 |
 |
�������́u�V�ˁv�̖@���i�����ҁF�i�D�������j ��������̍�i��������ǂ܂���Ă��O�������Ȃ���Ƃ́g�V�ˁh�ł���B[����]�@�W���f�B�X�E���������j�́A���{�ɂ��m�Ȃ̑��������A�����J�̂r�e��ƌ��A���\���W�X�g�B�Ȃ����v�� �i�e�D�|�[���Ƃ̋����w�F�����l�x�ŗL���ȁj �����b�D�l�D�R�[���u���[�X �ł���B���̓Ɠ��Ȏ��_�́A�r�e��P�Ȃ�Ȋw�����Ƒ������A�����ƍL���i�Љ�w�Ior�S���w�I���j�X�y�L�����[�V�����E�t�B�N�V���� �ƍl�����B���̂��ߏ��j�̕҂��u�N�Ԃr�e����I�v�ɂ́A�i�D�J�[�V���A�q�D�u���b�g�i�[�A�j�D���[�h�Ƃ����� �ȎҒB���W���B�ς�����Ƃ���ł́A�a�D�}���}�b�h�i�I�j���u���_�����v �Ȃ�Ă̂�����A�Ҏ҂̑��ǂԂ����������A���\���W�[�ł�����(�������A�b�D�X�~�X�A �`�D�x�X�^�[�Ƃ����������r�e��Ƃ��L�`���ƑI��Ă��}�X�j�B
|
||||||||
 |
 |
|
���Ă�j�̖@���i������:�|���v���q1956-) ���Ă�j�ͤ�V�����g���[�ł���
�m���߁n�@�|���ͤ���̏����Ȋw�G�b�Z�C�w����ȃo�J�ȁI�x�Ť�ŐV�̓����s���w���Љ��S���ҏW�҂Ɂe����
�ȃo�J�ȁI�f�Ƌ�������(�����Ă�������ɂ�)�������T�C�G���e�B�X�g�ł��顓��@���͂���ȓ����s���w�̍ŐV���ʂ�^�P�E�`����
�����������̡
�V�����g���[�ł��邱�Ƃ�(�̂̏o���������킯�Ť�܂�)���ɂ���Ȃ�������Ƃ����D�ꂽ�Ɖu��
�̏�������Ĥ���X�̖ړI���Ɖu�͂ɗD�ꂽ�I�X�̈�`�q�邱�Ƃł���Ȃ礃��X���V�����g���[�ȃI�X�����߂�͓̂��R��Ƃ����O�i
�_�@�ł��� �@�@����������(�L���Ȃ�) �@�A�炪���� �@�B�P���J������ �@�C�ؓ����̑̂����Ă��� �@�D�@�h�p������ �@�E����������̂����� �@�F�o ���������̐������� �@�G���q�̐���������������� �@�]�҂Ȃǂ͂��̖w�ǂ̏����ɍ��v���Ă��炸��v�킸���R���Ƃ��đ��݈Ӌ`�������̂łͤ�Ǝv���Y�̂ł���(�܂�������̏����� �������j�Ƃ��ăC���[�W�����̂͢���b�N�X���悭��^�Ɍ����s�ǣ�Ƃ������Ƃ���ł��褍��v���Ȃ��œ�����O�ł͂��邪)�B
[��]�@���҂̌��т͉�����R.�h�[�L���X�́e���ȓI��`�q�f�̍l��������₷���Љ�
���Ă��ꂽ�_������_�[�E�B���́e��̕ۑ��f���Ɏ����Ă�����ʓǎ҂̌����������X�͎̌̂�ł͂Ȃ�������̈�`�q���c������
�ɍs�����Ă���̂���Ƌ����Ă��ꂽ�̂ł���  Backmusic�F Dreams Come True �Monkey Girl Odyssey� |
||
 |
 |
 |
 |
|||||
�X�L���́u�l�����Ƃ�����v�̖@�� �i������:�X�L���A�o�D���@�����[�j ��X�͎��̒�������������ɂ����i�߂Ȃ��
�m���߁n�@�X���̓p����w�œ��{���w�A�v�z���u�����䂪���� ��\�I�N�w�ҁi�Ȃ����̑c���́A�����̌��M��X�L��j�B
�{�@���͂��̐X�����A�L���ȃu�b�N�E�f�U�C�i�[�ŐS�̗��l�ł�����Ȑ܋v���q��(1926-2021�j�ɑ������莆�̒��̈�߂ł���B
�Ȃ��ł���ۓI�������̂́A�X���̓Ɠ��ȕ��e�B �u�X�|�[�c����ɋ߂����炢�̒Z�����B���E��~���������̂����l�́A���F�̒P�߂̑����p�^�p�^�����Ȃ���A���������@�r�̊W���� �낤�Ƌ�S���Ă���B�v ����́A�Ȑ��Ƃ��̗F�l�Ή��l�q���i���̐l�����{���\����f�U�C�i�[�j�����߂ĉ�������́A�X���̃v���t�B�[���ł���B �����āA�X���ƕʂꂽ��A�Ή����͔ނ̂��Ƃ��u�G�l���M�b�V���Ń��[�����X�A�ӊO�Ȋ�������������ǖ��͂����v�ƌ����A���� �Ȑ��́u���͂��Ȃ����Ȃ���w�����x�ƌ������t�����������Ǝv���Ă����v�ƌ����Y����B������ɂ���A������\���鏗����l�ɁA����Ȉ�ۂ��c�������Ƃ����͊m���ł���B ����ȐX����"�l���ɂ��Ă�⼌�"���A�{�����炳��ɏE���Ă݂�Ɓ\�\ �u�{���ɂ��̐l���~�����������i�����j�����̕��������ꂢ�ɂ��āA�����̎d�����ꐶ�����ɂ��邱�Ƃł���B��������� �����������э���ł��܂��v �u�_�Ƃ������t�͂ˁA����͉����Ƃ����L���X�g�҂��A�������ł���Ă��邱�Ƃł������i�����j�_�Ƃ������t���y�X�ɂ����� �͂悭�Ȃ��Ǝv���܂����v�i���݂ɁA�Ȑ��͉Ƒ��̒��ŗB��A�L���X�g���M�҂łȂ������ȁj �u�i���̖{�́j���Y���ɓǂ�ł��炦��Ζ{�]�ł����v |
||||||
 |
 |